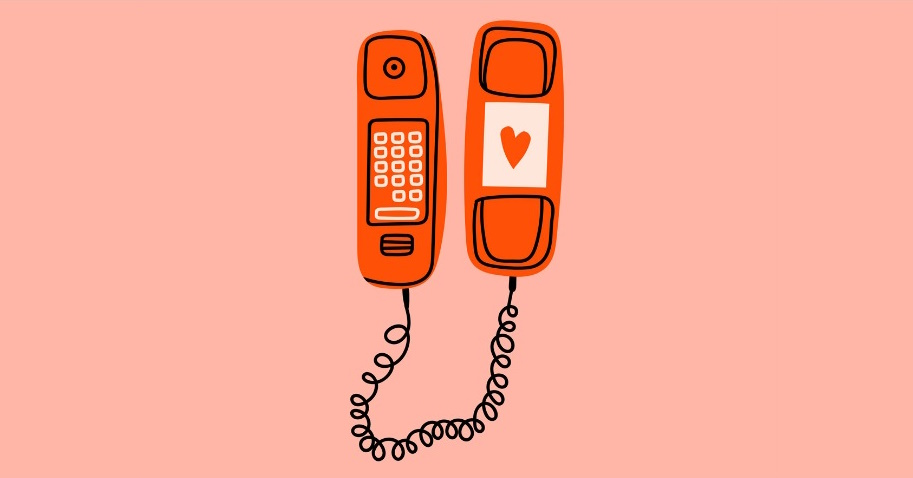働いている女性が妊娠したとき、妊娠中や産後の働き方と共に、「産休」「育休」について「いつから取れるの?」「申請はどうやってすればいいの?」と疑問に思うことでしょう。この記事では、産休・育休の基本から取得時期、便利な計算サイトまで、わかりやすくご紹介します。
産休(産前産後休業)とは?
産休とは、働く女性が出産前後に取得できる休業制度のことです。
産休を取れる条件
産休は、以下の条件を満たせば誰でも取得可能です。正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣労働者を含む労働者が対象となります。
・産前休業
出産予定日の6週間前から出産日まで(42日間)、希望すれば休みを取ることができる(双子以上のときは14週間前から)。
(労働基準法第65条第1項)
・産後休業
出産翌日から8週間(56日間)は、原則として働くことはできない
ただし、6週間を過ぎてから本人が希望し、師が認めた業務なら、復帰することも可能です。
(労働基準法第65条第2項)
産休は、女性労働者が請求すれば必ず認められる権利なので、安心して取得できます。
産休と育休の違い
・産休:出産前後の母体の健康と回復を目的とした休業。女性のみが対象。
・育休:子どもの育児を目的とした休業。女性・男性ともに取得可能。
産休は「出産のための休み」、育休は「育児のための休み」と覚えておくとイメージしやすいです。
産休(産前産後休業)はいつから取れる?
前述のとおり、産前休業は出産予定日の6週間前から。たとえば予定日が8月1日なら、産前休業の開始日は6月20日頃になります。産後休業は出産の翌日から8週間のため、自然分娩でも帝王切開でも同じです。
出産が予定日より遅れたら、産休はどうなる?
予定日よりも遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。なお、実際の出産が予定日より遅れて産前休業が延びたとしても、産後8週間は「産後休業」として休むことができます。
参考:「働く女性の心とからだの応援サイト」(厚生労働省)
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/gimu/kyugyo.html
育休(育児休業)はいつから取れる?
育休は、原則として子どもが1歳になるまで取得でき、女性だけでなく男性も取得ができます。出産後の産後休業が終了した翌日から取得可能です。男性の場合は、子どもの出生後8週間以内に「パパ育休(出生時育児休業)」を取得する選択もできます。
育休の期間
・原則:
(女性)出産翌日8週間経ったのち、子どもが1歳の誕生日の前日まで
(男子)出産当日から
・延長可能:保育園に入れない場合など、最長2歳まで延長可能
※育休取得については、休業開始予定日の1ヵ月前までに会社に申請する必要があります。
産休・育休の自動計算サイト・早見表紹介
「いつから、いつまで、産休・育休に入れるの?」と気になる方は、以下のような自動計算サイトが便利です。出産予定日を入力するだけで、産休・育休のスケジュールが一目でわかります。
<産休・育休自動計算サイト>
厚生労働省の「働く女性の心とからだの応援サイト 妊娠出産・母性健康管理サポート」
そのほか、民間企業が提供する「産休・育休スケジュール自動計算ツール」もたくさんありますので、ご活用ください。
<産休・育休の早見表>
また、印刷しておいていつでも確認ができる早見表(PDFでダウンロードが可能)も厚労省などから提供されています。
・産前休業・育児休業開始日 早見表(PDFが開きます)(厚生労働省ホームページ)
・産前産後期間一覧表(PDFが開きます) (全国健康保険組合ホームページ)
調査や実際の声からみる先輩パパママの育休取得事情
近年、日本では男性が育児に参加しやすいように、政府が制度を整えたり企業が意識を変えたりする動きが進んでいます。その結果、男性の育児休業の取得率は少しずつ増えています。また、以前は育休といえば女性が取るものとされていましたが、最近は共働きの家庭が増えたり、男女が平等に育児をするという考え方が広がったりしたことで、男性も積極的に育児に関わることが求められるようになっています。
厚生労働省が発表した「令和5年度 雇用均等基本調査」によると、男性の育休取得率は以前の調査よりも確実に伸びています。以下、調査の一部をご紹介します。
女性の育休取得率
・取得率:93.2%
前年度(令和4年)は85.1%だったため、8.1ポイント上昇。
過去最高水準となっています。
男性の育休取得率
・取得率:17.4%
前年度(令和4年)は17.1%のため、微増(+0.3ポイント)。
増加傾向ではあるものの、依然として女性に比べて大きな差があります。
とりわけ男性の育休取得率をあげるためには、企業側の制度や環境が不可欠です。
同調査によると、男性育休を推進する制度として、どのような制度が導入されているかを聞いた質問では、下記のような結果となりました。
<男性育休を推進する制度>
育児目的休暇制度の導入率:36.2%
配偶者出産時の特別休暇制度の導入率:79.3%
一方で、「制度はあるが利用が少ない」という声も見られ、今後の課題として「職場の雰囲気」や「業務の調整」があげられます。
【実際の声紹介】私たちの育休事情
高齢出産で産後すぐの育児に不安があったので、夫(パパ)に3週間ほど育休取得をしてもらいました。産まれてしばらく赤ちゃんだけ入院が続きましたが、一緒に通院したり、赤ちゃんを迎える準備をしたりでき、心強かったです。私自身は、1年間育休を取得しました。」(一人目を出産、夫婦で育休を取得した女性・正社員)
(一人目を出産、夫婦で育休を取得した女性・正社員)
「上の子が小学校1年生になるタイミングで、下の子を出産。
私(ママ)が産休育休取得の間に、慣れない小学校生活をサポートできるため、育休は1年間とりたいと考えています。
希望としては、夫(パパ)にも、パパ育休を取得して欲しかったのですが、出産前後の特別休暇は取得できましたが、パパ育休は業務の引継ぎができないため不可でした。」
(二人目を出産、現在育休中の女性・正社員)
まとめ
産休・育休は、パパとママが安心して子どもと向き合える大切な制度です。妊娠がわかった後、早めに情報収集と職場とのコミュニケーションをとることで、スムーズな産休・育休取得につながります。自動計算ツールも活用しながら、計画的に準備していきましょう。