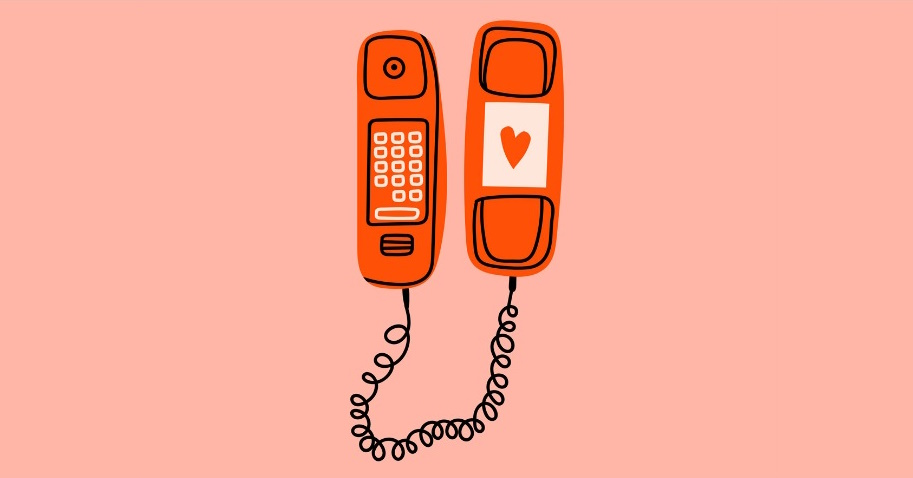夫婦で出産前後から役割分担を確認しておこう
赤ちゃんを迎える喜びとともに、出産前後は夫婦にとって大きな生活の変化が訪れます。家事や育児の負担が偏ることで、思わぬストレスやすれ違いが生じることも。
また、妊娠中や出産後のママは心身共に不調を抱えやすく、これまで以上にパパのサポートが不可欠です。
だからこそ、事前に役割分担を話し合い、お互いが無理なく協力できる体制を整えておくことが大切です。本記事では、夫婦でスムーズに協力し合うための、役割分担を行うためのポイントや実際に夫婦で使える「やることリスト」を紹介します。
【調査からみる】出産前後にママの不満が増える?!夫婦役割分担を確認する大切さ
改正育児・介護休業法の施行に伴い、ピジョン株式会社が行った調査*によると、家事・育児の役割分担について、以下のようなママとパパの認識にはさまざまな違いがあることが分かりました。
〈役割分担割合の認識の差〉
パパの自己評価が高い傾向がある:特に妊娠中、パパが自身の家事・育児への関与を高く評価する傾向があり、ママの評価との差が大きい
〈役割分担の決め方に対する認識の差〉
パパは、「2人で話し合って分担を決めた」と回答する割合が高い一方で、ママは「自然と決まった」と回答する割合が高い
この結果から、夫婦間でのコミュニケーションにズレが生じていることがわかります。
〈ママの時期別・分担の満足度の変化〉
・妊娠前~出産直後:ママ・パパともに約6割が分担に満足
・産後2カ月頃以降:ママの不満が約25%まで、増加する傾向が見られる
出産直後はママ・パパともに約6割が満足していますが、時間が経つにつれママの不満が増加し、特に、産後2カ月頃からは顕著になります。これは、ママの体が回復し、動けるようになることで負担を強く感じるためと考えられます。
〈家事・育児の内容の確認不足〉
家事・育児の全体像の把握や認識のすり合わせが行えていない家庭が半数以上(53.6%)
〈分担に関する課題の認識〉
・パパ:「時間が取れない」(55.0%)、「家にいる時間が短い」(44.6%)
・ママ:「全部自分で抱え込んでしまう」(46.1%)、「うまく相手に言えない」(33.9%)
パパは、分担に対して「時間」に課題を感じている一方で、ママは、「コミュニケーション」に関する課題を感じています。
出産前から、夫婦で話し合って役割分担を考えることが、産後の認識のずれをなくし、スムーズに家事・育児を協力し合うために必要だとわかります。
参考:「家事・育児における役割分担等に関する調査」ピジョン株式会社
(2022年1月21日~26日,全国に住む25~39歳の既婚で子を1人持つ男女 計1,249人対象)
パパにお願いしたい「やることリスト」手続き編
では、出産後、身動きがとりやすいパパにお願いしたい役割としては、どのようなものがあるでしょうか。手続き関連としては、以下のようなものがあります。
出産後に必要となる手続き
〈出生届の提出〉
期限:生まれた日を含む14日以内(国外で生まれた場合は3か月以内)
※時間外や夜間も受け付けしている
提出先:市区町村役場
パパができること
病院で出生届を受け取り、役所に提出する
戸籍謄本が必要な場合は事前に用意
〈健康保険の加入〉
期限:生後すぐに(1カ月健診までに)
提出先:勤務先の健康保険窓口 or 役所(国保の場合)
パパができること
会社の健康保険なら総務や人事に相談して手続きを進める
国保なら役所で手続きする
「児童手当QA」子ども家庭庁
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/faq/ippan#qa2
〈出産育児一時金の申請〉
期限:出生後2年以内
提出先:勤務先の健康保険窓口 or 役所(国保の場合)
パパができること
病院で「直接支払制度」(退院時に、支給42万円を差し引いた金額を支払う)が利用できるかどうかの確認
必要なら役所や会社で申請
〈(対象の場合)育児休業給付金の申請〉
期限:育休開始後
提出先:勤務先の会社 など
パパができること
パパも育休を取るなら会社に相談して申請
「育児休業等給付について」子ども家庭庁
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
出産前からはじめたい産後ケアに関する情報収集
ママの心身を休養・回復させ、安心して赤ちゃんのお世話を始めるために、産後ケアサービスの情報を事前に収集しておきましょう。
産後ケアを受けられる施設には、民間が運営するものや自治体が助成を行っている事業などさまざまな種類があり、提供されるサービス内容も施設ごとに異なります。
実際に利用するのは主にママと赤ちゃんですが、パパが情報収集を行うことで、出産前の体調が不安定な時期にママをサポートしやすくなります。
具体的にどのようなサービスが受けられるのか、下記の記事からもご覧いただけます。
関連記事:
産前から知っておきたい「産後ケア」とは どんなことをするの?https://sangocarelab.jp/know_sangocare/
「みんなの産後ケア」では、産後ケアを受けられる施設やサービスを助成実施自治体や所在地から探せます。産後ケアの探し方・検索は、下記からご覧ください。
https://sangocarelab.jp/howtosearch/
パパにお願いしたい「やることリスト」準備編
出産に関連する手続き以外にも、親戚や周囲の人への出産報告や赤ちゃんを迎えるためのグッズを購入したり、環境を整えたりすることも必要です。
準備することとしては、以下のようなものがあります。
周囲の人への出産報告、内祝いのお返し
〈親戚や共通の知人への出産報告〉
出産報告については、ママから直接伝える前に、パパから伝えた方がスムーズな人もいるでしょう。両親や親戚、共通の知人など、パパから出産報告する人のリストを作成しておきましょう。
出産報告では、以下の内容をシンプルにまとめると伝わりやすいです。
・生年月日・誕生時間、性別、体重・身長(伝える場合)
・赤ちゃんの名前(決まっている場合)
・ママと赤ちゃんの体調(簡単に)
・お礼や今後のお願い
〈出産祝いの「内祝い」の準備〉
出産後、お祝いをいただいた方へ「内祝い」を贈る際は、事前に準備しておくことが大切。そうすることで、出産後の忙しい時期でもスムーズに対応できます。パパがリスト作成や購入を担当すると、ママの負担を軽減できるので、積極的にサポートしましょう。
・リスト作成… 誰から・いくら・何をもらったかを記録し、内祝いの予算を決めます。相場としては、地域や関係性によってもさまざまですが、いただいたお祝いの1/2〜1/3程度を目安に考えましょう。
・品物選び、購入… 百貨店やオンラインショップなどで購入。のし・包装の確認も忘れずに。
表書きは「内祝」「出産内祝」+赤ちゃんの名前
・贈るタイミング… 生後1か月頃を目安に。入院中に来てくれた方には、その場でお渡しできるようにいくつか事前に用意しておくのも良いです。
赤ちゃんを迎えるためのベビー用品準備や環境づくり
その他にも、出産後すぐに使えるようにベビー用品の準備や、赤ちゃんのための環境を整えておくことも、パパにお願いしたい役割分担です。
〈ベビー用品の準備〉
ベビーベッドやチャイルドシートなど、組み立てや設置が必要なものを、出産後すぐに使えるように事前に準備しておきましょう。
また、おむつや衣類のストックなど、かさばる用品や細かな準備物も、身動きがとれるパパが準備できると良いでしょう。
〈部屋の環境づくり〉
赤ちゃんが少し大きくなったら、家の中の安全対策も必須になります。出産後、あらかじめ家具の角や電気コードのカバー、誤飲防止のための整
理整頓などを進めておくと安心です。
また、赤ちゃんやママの寝る場所の確保(明るさや室温の確認も)も、事前に決めておくと、ママが入院中にパパが準備をしておくことができます。
〈パパの心構えやサポート準備〉
パパ自身が基本的な育児の知識(沐浴の仕方、授乳や夜泣きのサポート方法など)や、妊娠中から産後にかけての女性の心身の変化について学ぶことも、赤ちゃんを迎える大切な準備のひとつです。
パパにシェアできる「やることリスト」
これまで紹介した、パパにお願いしたい役割分担を『やることリスト』にまとめました。パパとの役割分担を考える際のツールとして、ぜひご活用ください。